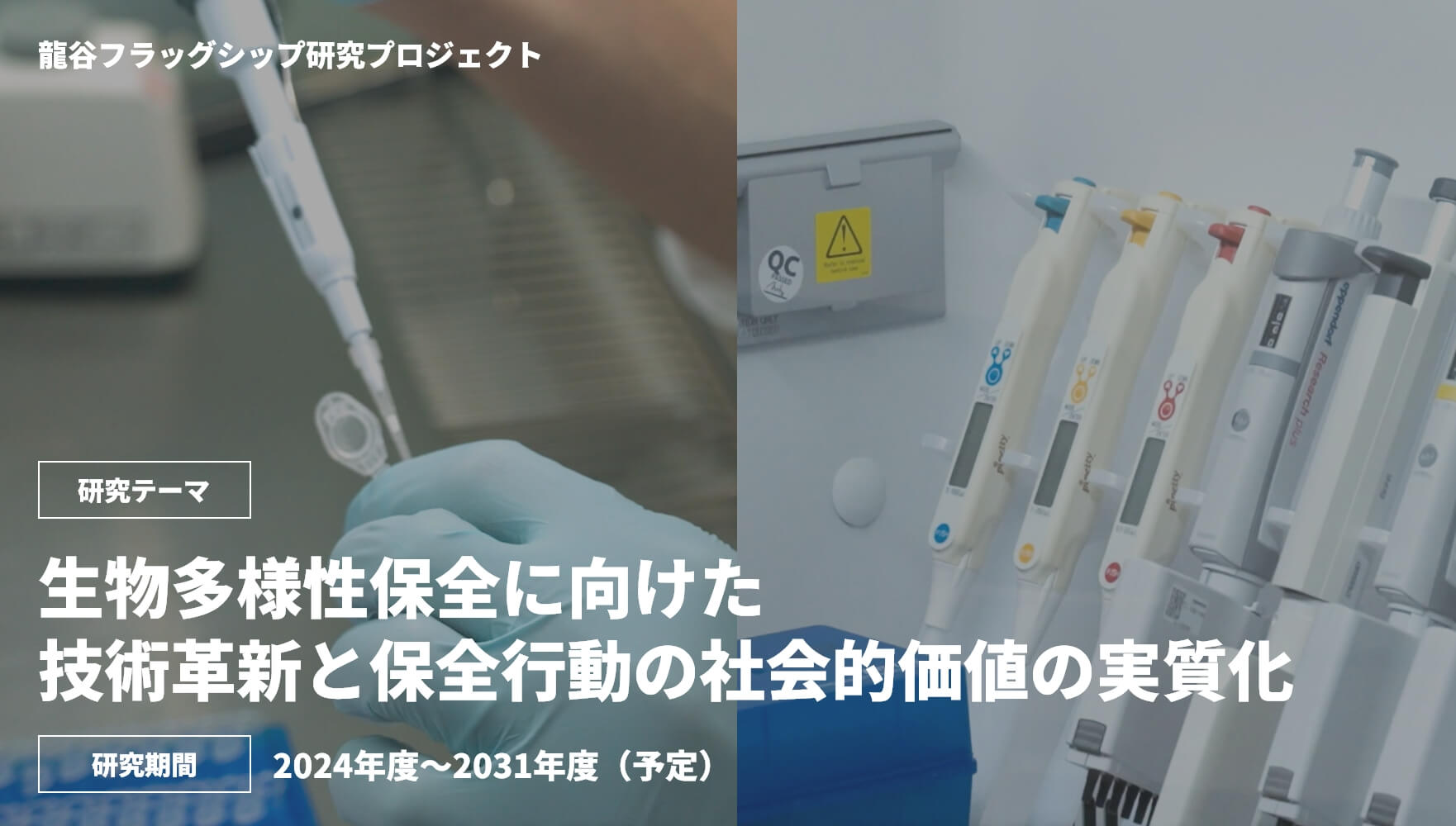
生物多様性科学研究センター概要
生物多様性保全に向けた技術革新と保全行動の社会的価値の実質化に向けて
2017年開設の龍谷大学 生物多様性科学研究センターは、新規の生態系モニタリング手法である「環境DNA分析」を主軸となる技術にすえ、生物多様性保全に向けた各種の活動や政策判断に高解像度の生物多様性データを提供することで、SDGsの達成に向けた社会貢献に寄与すべく、研究活動を展開してきました。環境保全の維持については、様々なステークホルダーが同じ土俵の上で議論し妥協点を求め、そしてそれぞれの立場で何ができるのかを考え続ける必要があります。
2024年度より本学の研究力を象徴する研究プロジェクトとして、「龍谷フラッグシップ研究プロジェクト」に採択され、新たに「生物多様性保全に向けた技術革新と保全行動の社会的価値の実質化」をテーマに掲げています。地球温暖化の問題には温室効果ガス排出量のような量的に可視化された指標がある一方で、生物多様性の低下の問題ではその価値の可視化が遅れています。当センターでは「環境DNA分析」等の本学が保有する先端的環境モニタリング技術を活用し、生物多様性情報の可視化と、その情報に基づく地元企業や行政に対するインセンティブの創出を進め、保全行動にヒトや資金が継続的に流れるシステムの構築を目指します。保全行動に経済的な意義を裏付けることで継続可能なシステムの成功例を作り、龍谷大学から発信します。
◎研究メンバーおよび業績は、センター公式HPをご覧ください。
https://biodiversity.ryukoku.ac.jp/
Key Projects
市民参加型の調査プロジェクト「びわ湖100地点環境DNA調査」

山中教授が2021年にスタートした琵琶湖の環境DNA調査活動。環境保護に関わるNPOや企業などの協力のもと、琵琶湖の100地点で水を汲み、生き物の生息状況を調査・分析。未確認だった外来種の発見やエリアごとの傾向の解明などの琵琶湖の生態系の可視化を行い、継続的に実施することで保全活動に有効なデータの蓄積を行っています。2024年度は滋賀県との共催事業として8月に実施しました。
【関連Page】
「びわ湖の日チャレンジ!みんなで水を汲んでどんな魚がいるか調べよう!」びわ湖100地点環境DNA調査
https://biodiversity.ryukoku.ac.jp/page-487/
フィッシュパス社と連携した「スマート環境DNA調査システム開発」


環境DNA分析のさらなる普及をめざして、福井県立大学発のスタートアップ企業である株式会社フィッシュパスと山中教授が連携して取り組む、漁協関係者向けのプラットフォーム開発。非専門家でも扱える「環境DNAの採水キット」をアプリと連携して使用することで、調査地の生態系を手軽かつ迅速に可視化することをめざしています。
【関連News】
スマート環境DNA調査システム開発プロジェクトにかかる記者発表を実施(2024.02.21)
https://www.ryukoku.ac.jp/nc/news/entry-14303.html