
生物多様性科学研究センターの山中 裕樹センター長(先端理工学部・教授)が、龍谷フラッグシップ研究プロジェクトにおける学際的研究を進めるべく、多様な分野で活躍する研究者と意見を交わす対談企画の第3弾。
今回は経営・経済農学を専門とし、海外進出する日本企業の研究、また学生の研究指導を通じ京滋エリアの企業との共同研究を進める金子 あき子講師(農学部)との対談です。
近年、中華圏の人々の食への意識変化を感じているという金子先生。また国内でも、食品企業のプロモーションで興味深い事例があるのだとか。当センターが構想する生物多様性認証制度を浸透させていくうえでのヒントを探りつつ、ディスカッションを行いました。
※発言は2024年11月取材時点のものです。
写真左:山中 裕樹教授(先端理工学部)、
写真右:金子 あき子講師(農学部)。以下、敬称略。
途上国の発展のために必要なモチベーションと取り組みの継続性
山中:金子先生は、食にまつわる企業の国内外でのブランディングや取り組みを研究されていますね。食品は消費者に身近な分野ですから、ぜひ当センターのプロジェクトを推進するヒントが得られればと、フードビジネスを専門とする金子先生にお声がけしました。
現在の専門は経営・経済農学ですが、ユニークな経歴をお持ちですよね。

金子:私は東京農業大学 国際食料情報学部を卒業し、食品関連の小売企業で勤務した後、JICAの青年海外協力隊員として西アフリカのセネガルで2年間活動を行いました。セネガルでの任務はPRODEFI(総合村落林業開発計画プロジェクト)という事業終了後のフォローアップを行うことでした。同プロジェクトは、地域住民による自主的な植林活動の促進と地域生産システムの改善を通じて、住民の生活向上と生態系の維持・回復を行うことを目的としていました。
山中:セネガルでは具体的にどのような経験をされたのですか?
金子:セネガルは農業や漁業を主な産業とする国です。しかし年間の降雨量が少なく、森林伐採などで土地がやせて井戸も深い、という厳しい環境です。私自身はPRODEFI終了後の村々の女性グループを対象に、農業による収入向上や地域活動の活性化を目指しました。具体的には10村ほどをバイクでまわって女性グループと会議を重ね、研修会や野菜栽培、マイクロファイナンス、種子の共同購入等を実施しました。はじめは新しい取り組みになかなか理解を得られないこともありましたが、収穫した作物によって収入が得られるようになると、徐々に参加者の活気が増したように思います。現地の人々にやる気になってもらうことの大切さを実感しました。
山中:当人にやる気になってもらうことの重要性は教育にも通じますね。その後、フードビジネスに興味を持ち、研究者になられた経緯とは?
金子:そうですね。国際協力の分野でもっと働きたい気持ちが膨らみ、専門性を磨くべく帰国して大学院に進学しました。そこで研究テーマに選んだのが「日本企業の海外進出」です。理由はJICA時代の経験に基づきます。私は政府開発援助(ODA)による支援終了後の地域を訪問した際に使われず放置された機械や資材を見て、国際協力を継続的に行う難しさを実感しました。同時に「企業が海外進出して永続的に事業活動を行うことが、途上国の発展のために良いのではないか」と考えたんですね。
そして研究を進めていたところ、自分が学んだ技術や方法論を多くの人々に広めたいと考え、教員の職に就いた次第です。現在の研究では、主に中華圏や新興国に進出している日本企業を対象としています。
海外進出する日本企業と、海外で求められるエシカルな商品への温度感
山中:近年、海外進出にあたって、各企業がどういった点に配慮しているかなど注目ポイントを教えてください。

金子:2024年10月に私は毎年学生を引率して香港のフードエキスポに参加しています。出展企業の業種はさまざまですが、香港は健康や環境に対する意識が高く、ヘルシーなものや環境に配慮された商品が多い印象でした。
特に今年は香港フードエキスポ全体で有機食品や植物性食品など環境や健康に配慮されたものが多く、日本からの出展者の食品もエシカルなものが目立っていたことが興味深かったです。加えて香港は多国籍なので、ヴィーガンやハラール認証商品に対する注目度が日本より高いようです。
山中:たとえば日本国内でインバウンドを意識した商品には素材に抹茶や金箔を使ったり、ラベルに相撲力士や富士山が描かれていたりと「ザ・日本」を前面に出したものが多い気がするのですが、展示会に出展される日本企業の商品はそういったものではないのですか?
金子:もちろん日本的な味わいもウケは良いのですが、インパクトよりも良質なもの、安全性の高いものが求められています。まず商品価値として「素材のお米は○○産にこだわっています」「○○に配慮して製造しています」といった魅力を打ち出し、その上でデザインも洗練されたものでブランディングする企業が増加傾向にあると思います。
センターが構想する地域発「生物多様性認証」。一斉に浸透させるのは難しい?

山中:金子先生が詳しい食の安全性アピールや企業ブランディングについては、当センターの活動にヒントをもたらしてくれると期待しています。
今、センターで立ち上げようとしているのが「生物多様性ステークホルダー会議」です。滋賀県内の農林水産業や製造業の方、行政や金融などさまざまな業種・立場の方に入ってもらうべく準備をしていますが、そこで必要だと考えているのが、明確な指標の創設です。たとえば生物多様性に配慮した食品の認証制度で「レインフォレスト・アライアンス認証」などがありますが、ネイチャーポジティブに向かうには消費行動を変えることが重要ですから、滋賀県内のローカルでも指標・ツールを作り、認証制度やロゴマークの掲載権利付与などを考えています。
金子:認証マークを商品パッケージに貼るって、わかりやすくて良いと思います。ただ、問題はその認証の認知度をいかに高められるかですよね。
これは私見ですが、ある程度ターゲットを定めてみるのはどうでしょう。ヨーロッパでは何かしらの認証マークのついた商品が非常に多く、消費者が認証マークの情報を元に商品を購入することが当たり前になっています。ですが日本ではまだ一般的ではありませんよね。エシカルな商品に対して関心のない層まで含めて、広くアピールすることも大切ですが、関心のある消費者へ着実に届けることが重要だと思います。
近年は国内でもエシカルな商品を集めた小売店が増えてきています。この現状に鑑みると、最初にアプローチすべきは、そういったショップや商品を選ぶ消費者層ではないでしょうか。
まずは、エシカルな商品・サービスを理解した上で、値が多少張ってでもお金を払ってくれる人の存在が必要です。生物多様性に関心のある消費者が集まる場所に商品を置いてもらい、理念と活動を着実に届ける。そしてそこを起点に、今はあまり関心のない層にも徐々に認知度を上げていく。こういった段階的なマーケティングも有効な手段の一つだと考えます。

山中:たしかに、大々的に広めるという展望が念頭にあったので、少しずつ着実にという視点が抜けていたかもしれません。ところで認証マークの食品を多く扱う小売店などは、少し価格帯が高い印象があります。生物多様性を謳った商品を市場に出す場合、価格設定などもこだわる方が良さそうでしょうか。
金子:そうですね。モノを売るとなると、できるだけ安い方が良いだろうと想像される方もいると思いますが、ある程度高価な方が“引き”のある商品もあります。特に、環境や健康にこだわった食品はその傾向があります。いろいろと手間がかかっているはずなのに安い、となると逆に信用してもらえなかったりする。ですから、企業が無理に価格を下げる必要はないと思います。適正な価格帯で買ってくれる消費者に届けるところから始めること。これがすごく重要かなと思います。
また、販売時には認証の説明に加えて、この商品で私達の生活がどのように保たれるのか、ストーリーを一緒に伝えていくことも大事ですね。近年、商品の背景にある経営者の考えや生産に関わった従業員の思いを消費者に伝える取り組みを実施している企業が非常に増えていると感じます。
「どこにニーズがあるか」を捉え、商品価値・認証価値を高めることが成功のカギ
山中:各企業いろんな商品企画・プロモーションを実施されていると思いますが、金子先生から見て興味深いケースがあれば教えてください。

金子:私は龍谷エクステンションセンター(REC)を通じて豆腐機器メーカーのカワニシ(本社:京都府久世郡久御山町)さんをご紹介いただき、おからの廃棄削減について共同研究をしています。その関係でおからの利活用に関心を持っていたところ、大阪でベーカリーを営むラパン(本社:大阪府吹田市)さんがおからを用いた理想的な商品を販売されていることを知ったのでご紹介します。実はラパンさんも今年の香港フードエキスポに出展されており、会場で知り合うことができました。
ラパンさんは、おからを原料とするヘルシーで美味しいスナックを製造しています。ヴィーガン認証、グルテンフリー、低GI食品であることなど、商品の特徴をうまくパッケージに掲載し、おしゃれなスイーツとして販売しています。今、とある市場ですごくヒットしていて、それがなんとホテル業界です。客室用のお茶菓子として「日本の伝統食であるおからを用い、サステナブルなフードだ」と、特にインバウンド客の多い業界で話題性があるそうです。
ラパンの久保副社長にお話を伺うと、「おいしいものを作ることは大前提として、それだけでは売れない」と。どういった場所で、どんなパッケージで商品の価値を高めるかに非常にこだわってらっしゃいました。プロモーションって中身も重要ですが、やはり「自分たちの商品がどこで売れるのか」を徹底的にリサーチし、それに合わせたパッケージや宣伝方法を追求することが重要だと改めて勉強になったケースです。
山中:私は販売や流通が専門外なので、とても勉強になります。
たしかに、モノがどれほど良いかとか、認証をクリアしたとかいっても、気にかける人がいなければその価値は伝わらないですよね。生物多様性の認証マークにしても、消費者や関わる皆さんの同意・共感を得ることではじめて意味あるものとして活用されるのだと思います。作る人がいてPRする人がいて、買う人・食べる人がいて、廃棄に関わる人がいるからこそ成り立つ。となると、これまで認証制度を創設することにばかり意識がいっていましたが、消費者の行動変容を引き起こすには私の想像よりも遥かに多分野の人に関わってもらう必要があるのだとイメージが掴めてきました。
金子:一般層をターゲットにした例も一つ紹介します。カゴメ株式会社が2019年に長野県富士見町に創設した「カゴメ野菜生活ファーム富士見」は、同社の工場周辺に広がる遊休農地だったところに、「農業・工業・観光」を一体化させた体験型テーマパークを作ったものです。
来場者は農場での収穫体験や工場見学、レストランでの野菜中心の食事を楽しむことができます。敷地内の農場には、フクロウの止まり木があり、虫や爬虫類が生活できる場所も設けられています。来場者は、体験を通して生きものと共生する農場の取り組みについても学ぶことができます。「当社の商品は体と環境に良い商品ですよ」と消費者にわかりやすく伝える存在として機能していて、上手なアプローチだと思います。
生物多様性活動に関する認証を制度化するに関しても、このように企業を“見える化”する取り組みも重要になってくるのではないでしょうか。
山中:ともすると企業ブランディングの側面に目がいきがちですが、こういう取り組みにお金を回せる企業が多くの人に理念を知ってもらうことって、実は想像以上に業界的な波及効果があるんでしょうね。農業のやり方が時代とともに変わっているとか、生き物に配慮した作り方はこういう方法がありますよとか、中小の農業法人だとそこまで手が回らないこともあるでしょうから。
金子:そうですね。大企業のこういったPR活動は、多くの消費者に環境意識を高める場を提供するという意味で、業界全体に良い影響を与えると思います。
今年、アフリカのタンザニアにある日本人が経営するコーヒー農園を訪問しました。タンザニア産コーヒーの主要輸出先の一つが日本です。コーヒーは環境負荷の高い作物だとされていることから、持続可能なサプライチェーンの確立に何らかの関わりを持ちたいと関心を寄せる日本企業が非常に多いそうです。
またJICAタンザニア事務所を訪問した際、現在JICAではSDGsに取り組む企業やタンザニア進出を目指す企業に支援を行っていることや、日本の企業から「タンザニアの環境や社会を良くする活動がしたい」という問い合わせが増えていることを知りました。
山中:従来は環境配慮型の生産というとコストがかかり、直接の売上に結びつかないと思われてきました。まだ実感に乏しいですが、こうしたお話を聞くと、日本の経営層の間で「会社の未来のためにはエシカル思考が必要だ」と認識が広まっているのでしょうか。

金子:そのようですね。ただ一方で、株主や消費者の意識は追いついていないようだという話も耳にします。となるとやはり、環境配慮・生物多様性の課題に取り組む姿勢が企業経営でどのようなメリットがあるか、各ステークホルダーにわかりやすく伝えていく課題があると思います。
今回ご紹介した事例のように企業が率先して環境に配慮した取り組みを示すことで、環境を守ることや生物多様性を維持することの大切さが社会に浸透してゆくといいですね。
山中:ネイチャーポジティブって、脱炭素と同じく世の中全体で向かうべき方向ではあるのですが、企業活動には大きなコストかかる。誤解を恐れずにいえば、当センターが進めようとする生物多様性保全の活動も理念は美しいものの、企業の皆さんを短期的な採算が保証できない活動に向かわせるものです。
その点が大きな懸念であり、経営者の方々にどう説明すればいいのだろうといつも悩むのですが……。タンザニアに問い合わせる企業が増えているという事例を聞くと、希望が感じられます。今後は、そういった決断をした経営者の方々にもお話を聞いてみたいと思いました。
当センターでも具体的な活動を進めていきたく、滋賀県内での農業生産品のブランディングについて、特定の地域で実施するなどを計画中です。実行の折には、ぜひ金子先生にも参画してもらえると嬉しいです。
プロフィール

金子 あき子(Akiko Kaneko)
龍谷大学農学部・講師
専門は経営・経済農学。東京農業大学卒業後、食品小売企業に勤務。JICA青年海外協力隊員としてセネガル共和国にて農業開発と野菜栽培の指導に従事した後、JICA草の根技術協力事業国内調整員、桃山学院大学大学院経済学研究科博士前期・後期課程、桃山学院大学共通教育機構講師を経て、2019年より現職。博士(経済学)。
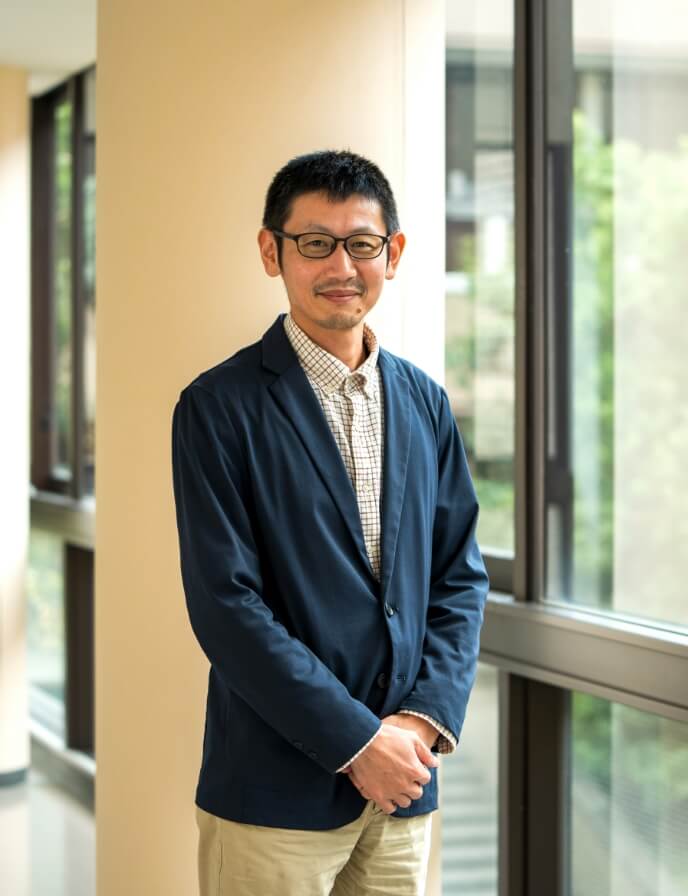
山中 裕樹(Hiroki Yamanaka)
龍谷大学先端理工学部・教授
京都大学大学院 理学研究科修了。博士(理学)。魚類生態学者。一般社団法人「環境DNA学会」設立メンバーの一人 。2009年より、滋賀県などで環境DNAによる生物相調査を行うとともに、生物量推定のための新技術開発や環境評価への応用技術研究も推進中。生物多様性科学研究センター長。

