
「生物多様性の損失を食い止め、自然を回復軌道に乗せる」ネイチャーポジティブの実現には、各地域の生物多様性に関する情報を正確かつ継続的に把握するのはもちろんのこと、収集された情報を科学的知見に基づいて保全行動につなげることが必要とされます。さらには、生物多様性に対する市民の理解促進や担い手の育成など、さまざまなステークホルダーとの連携強化も重要な課題です。
このゴールに向けて、生態学者が果たすべき役割とは何なのでしょう? またステークホルダーとの連携強化に必要なこととは? きょうと生物多様性センター長を務める湯本貴和氏を特別ゲストに迎え、二人の生態学者が語り合います。
※発言は2024年12月取材時点のものです。
写真左:山中 裕樹教授(先端理工学部)、
写真右:湯本 貴和教授(京都大学名誉教授/きょうと生物多様性センター)。以下、敬称略。
滋賀と京都で生物多様性情報を収集し、ネイチャーポジティブの意義を伝える
山中:湯本先生は大学院時代の恩師であり同分野の大先輩なのですが、前職の総合地球環境学研究所でお世話になったことから親しくさせていただいています。
湯本:昔から付き合いが長いよね。
山中:今日は先生と、ネイチャーポジティブの流れの中で私たち生態学者が感じている課題や、求められる役割についてお話できればと思っています。まずは、きょうと生物多様性センターについてご紹介いただけますか?
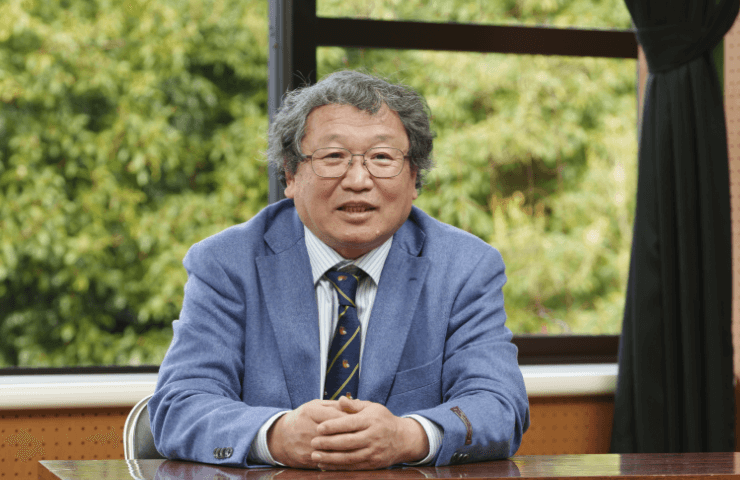
湯本:きょうと生物多様性センターは2023年4月に発足したばかりの組織ですが、府市協調で京都の生物多様性情報の集約拠点をめざして、また生物多様性の意義を発信することをミッションに頑張っています。
京都は近隣府県に比べると研究者の層は非常に厚いのですが、公立の自然史博物館がないことが大問題なのですよ。文化財系の博物館は多いのですが、自然史系といえば京都大学総合博物館ぐらいです。滋賀県立琵琶湖博物館や大阪市立自然史博物館のように、これまで京都の公立館として専門家を抱えて京都府や京都市の生物多様性情報を集約している拠点がなかったので、その役割を当センターでささやかながら担うことを目的のひとつとしています。
生物多様性の意義の発信という点では、我々のような生き物マニアをしっかり取り込みつつ、虫や落ち葉は要らないと考えるような人々にも生物多様性の意義を伝えることが大事だと考えています。
さらに企業に対しては、生物多様性への配慮あるいは無配慮が、いかに経営上のメリットやリスクにつながるかの理解を進めていただこうとしています。ですが正直なところ、企業の方々は困惑されていますね…。

山中:私がセンター長を務める龍谷大学 生物多様性科学研究センターは、瀬田キャンパスを拠点に滋賀県で活動しています。センター自体は2017年4月設立と、ネイチャーポジティブという名称が誕生する前から活動をはじめ、生物多様性に関する高解像度のデータを提供することで、SDGsのゴール達成に向けた社会貢献を目標の一つとしてきました。
そもそも生物多様性情報が不足していたことが、学問的な前進を停滞させ、水産資源を厳密に管理できない状況を生み出していました。だからこそ、情報取得をすみやかに進めなければならないという問題意識から、同時期に出てきた環境DNAという分析技術を活用し、技術の精密化を進めるとともに社会実装を実現するためにセンターを立ち上げたのです。
もちろん生物多様性情報の取得には、環境DNAというワンツールだけでは十分ではありません。そこで本学先端理工学部や農学部の研究者らを取り込み、さまざまな環境観測や環境対応の技術や知見、人材やネットワークを提供するハブとしてセンターを機能させたいと考えてきました。
ですが、やはり私たちも、きょうと生物多様性センターと全く同じ問題を抱えています。2024年4月から環境DNA分析等の本学が保有する先端的環境モニタリング技術を活用し、保全行動の社会的価値の実質化に向けた研究プロジェクトをスタートしたのですが、企業の協力を仰ごうにも、やはり生物多様性保全の意義がCSR担当者を超えて経営陣にまで伝わらない。早急に生物多様性情報を可視化する必要があると感じています。
生物多様性情報の可視化に欠かせない分類学者がいなくなる危機
湯本:生物多様性情報を明らかにと言っても、そもそもそれがいかに面倒臭いものかということを、ほとんどの人が知らないことが問題です。
今日の対談の舞台である京都府立植物園でいうと、ここに生息している被子植物やシダ類、鳥や蝶については大体わかっているんですが、蛾や甲虫といったその他諸々の昆虫については不明です。そもそも、ひとりで昆虫全般がわかる専門家というのは存在しようがないからです。
私はアマゾンなどの熱帯雨林でフィールドワークをしてきた人間ですが、現地では名前がついた昆虫は一握りで、何千万種もの未記載種がいる世界なんですよ。しかも5ミリ以下の昆虫になってくると、顕微鏡を使って詳細に調べなければいけません。
山中:湯本先生は学術的な手続きを踏んで新種を記載された経験もありますよね。今の時代、先生のようにフィールドに出て、直に調べて判断できる人材が貴重だと思います。
湯本:東南アジアの熱帯雨林で発見した「ユモトゴキブリ」ですよね!私だけでなく、京都は大学研究者や中学高校の理科教員、在野のアマチュア研究者が昔から多く、彼らがコツコツ作り上げた標本もあってポテンシャルは高いのです。ただしその標本を保管する博物館がないことが問題で、研究者自体も高齢化していることから10年後には標本の大半が失われる可能性があることに強い危機感を覚えています。これをいかに繋ぎ止め、若手をどうリクルートするかが課題ですね。
そこで私は、環境DNA分析技術が意味を持つと思うのです。通常なら、何十年もの教育や修練を経て育つ専門家が何十人と揃わないとできないことが、この技術を使えば一つの研究室レベルで済みます。それはとてつもないメリットでしょう。
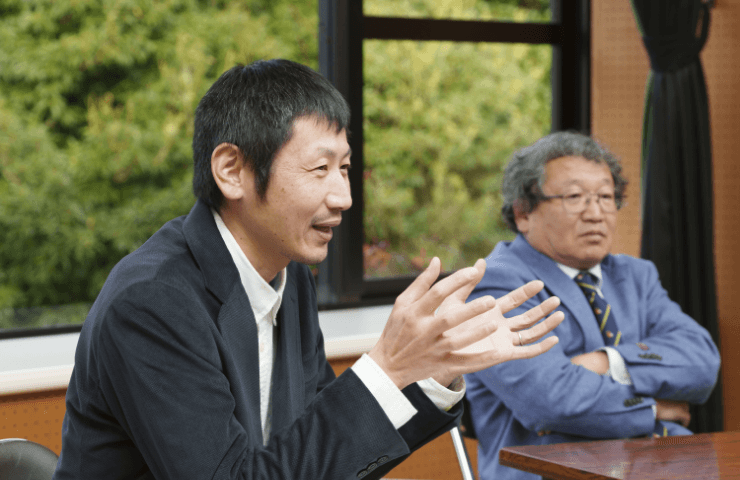
山中:ですが環境DNA分析技術にも課題があります。この技術の開発を始めたのが淡水魚類の研究者でしたので、現状では魚類を判別するアプリケーションに偏っているのです。植物や昆虫といった陸上の生態系のサンプル情報を収集していくには、答え合わせができる専門家の協力が必要です。
たとえばある地域の空気から環境DNAを採取して「ここにはAとBとCの鳥がいる」と分析結果を伝えても、鳥類の専門家による裏付けがなければ不確かです。ですがその答え合わせができる専門家がリタイヤしていなくなる、本当に今そのフェーズにきているんですよ。
湯本:分類学の専門家の不足は世界的にも問題になっているのですが、日本は特に酷いですね。
山中:もちろん今後、環境DNA分析技術を陸上に展開していける可能性は十分あります。生物サンプルからきちんとDNA配列のリファレンスデータベースを作っておけば、 環境DNA分析による野外調査で生物多様性情報の一定はデータ化することはできるでしょう。しかしそれには生物分類ができる方が現役でいなければなりません。
DNA配列を登録したオープンなデータベースがあるのですが、中には間違いもあります。実際に、私が主に分析している魚類のデータの中にも同定の間違いであろうと思われるものが幾つもありました。やはり標本の元となる生物サンプルを見て正誤を判断できる専門家がいないと間違いを防げません。
湯本:分類学者がいなくなる危機、これは2〜3世代後にはもっとリアルな課題になるでしょう。元々多くはなかったとはいえ旧帝大系の大学には分類学の研究室があったのですが、今やその研究環境がどんどん失われています。ここについてはもっと危機感を発信していきたいと思っています。
生物多様性への関心や危機感を企業・自治体のトップに抱いてもらうには、何が必要か

山中:冒頭でもお話ししましたが、一般の方や企業経営者に生物多様性について興味を持ってもらうことが課題です。特に企業に向けては、経営に関わるメリット・デメリットを提示する必要があると考えています。
湯本:そうですね。私は生物多様性に関する3つの価値の合わせ技でいくしかないと考えています。まず、生物多様性のある水準を下回ると生態系が維持できないという「機能的価値」。次に、将来世代に再生不能あるいは再生に大きなコストのかかる生物種を残すことで得られる「遺産的価値」。そして、生き物の減少や絶滅が我々にも影響する環境悪化を予見する「指標的価値」の3つです。
また経営層に向けては、京都では観光産業と紐付けて説明するのが一つの方法だと考えています。京都の観光資源は自然資源でもありますので、私は景観の重要な要素としての生物多様性の大切さを言い続けているんですよ。
山中:滋賀でも観光という軸はありだと考えています。いま考えているのが、琵琶湖の生き物や山の生き物・森の魅力を伝えるエコツーリズムを企画し、その費用計算に環境負荷への収支を含めて本当のツアー費を出すことです。
それを生物多様性科学研究センターの面白い取り組みとして、滋賀県内の自治体と組んでやってみたいという話をしているんですよ。研究メンバーには工学系の研究者もいるので、全部のエネルギー計算ができますから。
自然の中に人が入ると何がどれだけ排出されるのか。その処理にどれだけエネルギーがかかり、温室効果ガスがどれくらい排出されるのか。それをプラマイゼロにするには、この価格設定でないとツアーが組めないんだ、ということを示すことができれば面白いですよね。
生き物に興味がなくても環境を守ることには理解がある人は、環境負荷を無視したツアーよりもこちらを選ぶのではという期待があります。またそれが社会実装として広がるのが理想ですね。
湯本:そういうやり方も良いですね。一方で、社会システム全体からみて優先順位が低いことが気になります。生物多様性条約には環境省だけでなく農林水産省や国土交通省、経済産業省も関わっているのですが、まだまだ本気ではないように感じます。各省が生物多様性保全とは逆行するような事業に補助金を出すことも見受けられますからね。
企業や自治体がネイチャーポジティブに取り組めるよう、やはり国に一元的な政策を打ち出してもらわないと2030年の実現は難しいでしょう。そのために我々も日々、企業や自治体のトップに生物多様性の意義を理解してもらおうとしているのですが…。今の世の中ではわかりやすさが求められますが、生物多様性は元来わかりにくいものなんです。特に組織のトップの方々にこそ、このわかりにくさを理解してもらいたい。
生物多様性情報を社会で活かすために、国や制度を動かすことも視野に連携を
山中:やはり発信し続けることが必要だと考え、生物多様性科学研究センターでは、企業や行政関係者などと勉強会を立ち上げる計画です。きょうと生物多様性センターでは2024年9月に「企業のための生物多様性セミナー」を開催され、TNFDに取り組む企業の方々も登壇されていましたね。
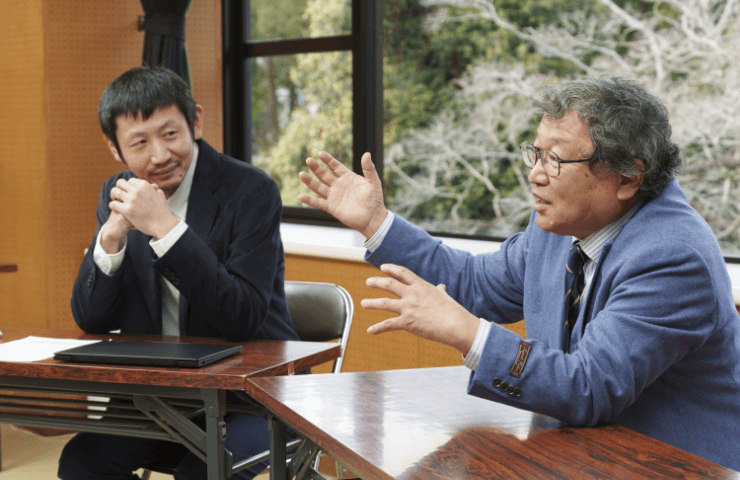
湯本:まずはシンポジウムで対話のチャンネルを作り、それを積み重ねていくことが大事です。生物多様性の評価は非常に難しいのですが、京都にはユニークな計測技術を持つ企業が多く存在しますので、そうした企業と組んで環境観測が簡単にできるツールを開発するのはどうかと個人的に考えています。生物多様性評価の世界基準がまだ存在しない状況ですから、世界基準を京都で作るのは良いアイデアではないかと。
山中:環境先進国のヨーロッパでは、環境DNA分析に取り組むとなると、研究者や技術者のチームだけでなく、政策や法分野での実行を考えるメンバーまでもが集まり、学会のような組織を作って実働しているようです。
なぜ法かというと、これはアメリカの生態学者から聞いた話ですが、いわゆる科捜研のような機関が犯罪の疑いをかけられた人のDNAの痕跡を採取・鑑定した時に、DNA分析のプロトコルを全てクリアした質が担保されているデータでないと法廷では証拠として扱われない。たとえ将来的に生物多様性を意図的に減らした者に罰則を与えるということになっても、環境DNAの手法で採取・分析したものが法的に認められたデータでなければ、証拠としては扱われないというのです。なるほどなと、実感しました。
環境DNAなどの環境モニタリング技術を法制度に活用するためにも、国や制度を動かすことも視野に、私たち生態学者がステークホルダーとの連携を強化しないといけませんね。
湯本:この点においては、龍谷大学が私立大学であることが強みになると思います。多くの国立大学は組織が大きく、新しい組織を立ち上げるには文部科学省にお伺いを立てるところからの意思決定のプロセスが長すぎます。その点、私立大学は学長の裁量が大きいと思いますので、よりスピーディーに動けることでしょう。そこに生物多様性科学研究センターの皆さんの力が生きてくるような気がしますね。
プロフィール
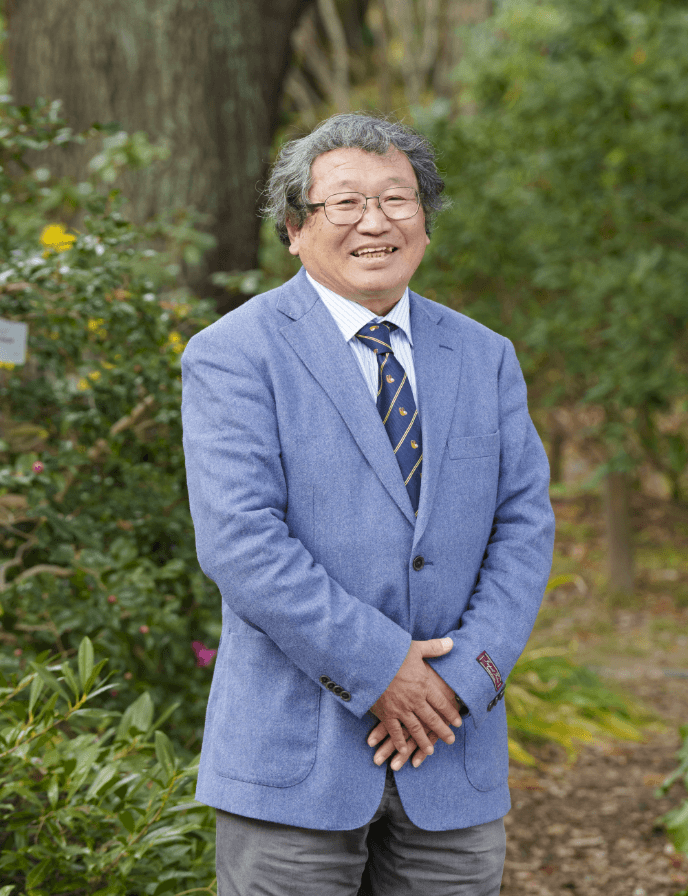
湯本 貴和(Takakazu Yumoto)
京都大学名誉教授、
きょうと生物多様性センター長
京都大学大学院 理学研究科修了。博士(理学)。植物生態学を基礎に植物と動物の関係性を綿密に調査し、熱帯雨林での探検調査は数知れず。総合地球環境学研究所教授、京都大学霊長類研究所教授・所長を務め、退官後も食からAIまで多方面で活躍中。2023年4月より、きょうと生物多様性センター長。

山中 裕樹(Hiroki Yamanaka)
龍谷大学先端理工学部・教授
京都大学大学院 理学研究科修了。博士(理学)。魚類生態学者。一般社団法人「環境DNA学会」設立メンバーの一人 。2009年より、滋賀県などで環境DNAによる生物相調査を行うとともに、生物量推定のための新技術開発や環境評価への応用技術研究も推進中。生物多様性科学研究センター長。

